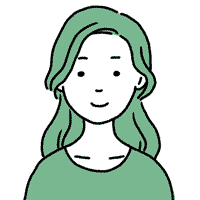更新日:
公務員におすすめの住宅ローンと比較のポイント
- 銀行の選び方

公務員は住宅購入時に有利。知っておきたいおすすめの住宅ローンと比較のポイント
国や地方自治体で働く公務員は、勤務先の安定性や、給与・ボーナス・退職金などの待遇の良さから、住宅ローンを組む際は有利と言われています。住宅ローンの審査に通りやすいことはもちろん、その銀行が提供する最も低い金利(再優遇金利)が適用されるケースもめずらしくありません。
これから住宅ローンの借り入れを検討している公務員の方は、金利が低い代わりに審査が厳しめの住宅ローンや、公務員向けの優遇金利を提供している住宅ローンなどを視野入れてみてはいかがでしょう。
今回は「公務員におすすめの住宅ローン」をテーマに、公務員が住宅ローンを比較・検討する際のチェックポイントを解説。金利やサービス内容の充実したおすすめの住宅ローンもあわせてご紹介します。マイホームの購入を考えている公務員の方はぜひ参考にしてください!

住宅ローンはどこで組む?借入先の銀行の選び方 5つのポイント
住宅ローンはどの銀行で組むのがおすすめ?金利や団信、諸費用など、住宅ローンの借入先の銀行を選ぶ際に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説。
公務員におすすめの住宅ローン 比較する際の5つのポイント
公務員におすすめの住宅ローン 比較する際の5つのポイント

住宅ローンはメガバンク・地方銀行・信用金庫・ネット銀行など、多くの金融機関が取り扱っています。
住宅を購入する際は、不動産会社やハウスメーカーから住宅ローンを紹介されるケースがほとんどですが、購入者が自分で住宅ローンを選ぶことももちろん可能です。
特に公務員は、住宅ローンの審査に通りやすい傾向があるため、購入前にいくつかの住宅ローンに目星をつけておけば、より有利な条件の住宅ローンを利用できる可能性が高まるでしょう。
本チャプターでは、複数の住宅ローンを比較する場合に最低限チェックしておきたい5つのポイントを解説します。
- 公務員におすすめの住宅ローン 比較のポイント
1変動金利か固定金利か
![]()
住宅ローンの金利タイプは大きく「変動金利型」と「固定金利型」に分かれます。
変動金利型は半年に1回の頻度で、日本の政策金利に連動する「短期プライムレート」を反映し、政策金利や短期プライムレートが上下した場合は、その影響を受けて変動します。
変動金利型の場合、固定金利型と比較すると金利水準は低く、ネット銀行を中心に年0.5%を切る住宅ローン金利を実現している金融機関もあります(2024年9月時点)。
変動金利型のメリットは、金利が低い分、利息が少なくすみ、返済額を抑えられる点。デメリットは、金利が上昇し返済額がアップする可能性がある点です。

住宅ローンの金利が上昇したらどうすればいい?住宅ローンを新規で借り入れるとき、借り換えを考えているとき、今の住宅ローンを引き続き返済していきたいときなど、3つのパターンで、金利上昇の際の対処法を解説します。
変動金利型のメリット・デメリット
- メリット
-
- 金利が低い分、利息が少ない
- 返済額を抑えられる
- デメリット
-
- 金利が上昇し返済額がアップする可能性あり
固定金利型は、返済中の金利がずっと変わらない金利タイプです。金利は、国債市場で取引される「新発10年国債利回り」と呼ばれる指標に連動して決まります。
金利水準は変動金利型と比較すると高く、例えば、長期固定金利型住宅ローン「フラット35」の場合、住宅ローン金利は年1.5~1.8%前後で推移しています(2024年9月時点)。
固定金利型のメリットは、金利を固定できるため返済計画にズレが起きない点。デメリットは、金利が高いため、総返済額が膨らみやすい点でしょう。
固定金利型のメリット・デメリット
- メリット
-
- 金利を固定できるため返済計画にズレが起きない
- デメリット
-
- 金利が高いため、総返済額が膨らみやすい
その他、一定期間の金利を固定する「固定金利選択型」も人気の商品です。これは、2年、5年、10年などあらかじめ決まった期間の金利が固定されるタイプで、固定期間の終了後は改めて金利タイプを選択し直すことになります。
金利水準は金融機関によってまちまちで、固定期間が数年の短期の場合は、変動金利型より低い金利を提供している住宅ローンもありますが、固定期間が長くなるほど金利が上昇する点には注意しましょう。
固定金利選択型のメリットは、返済開始直後の一定期間、金利を固定することで資金計画が立てやすくなる点。デメリットは、固定期間明けの金利水準が、固定期間中と比較すると高くなるケースが多い点です。
固定金利選択型のメリット・デメリット
- メリット
-
- 返済開始直後の一定期間、金利を固定することで資金計画が立てやすい
- デメリット
-
- 固定期間明けの金利水準が、固定期間中と比較すると高くなる
このように、住宅ローンを比較する際は、最初に金利タイプを決め、「低金利で返済額を抑えるか」「金利上昇リスクを避けてコツコツと返済するか」「その中間を取るか」といった方針を考える必要があります。
2金利水準
![]()
住宅ローンの金利は、低ければ低いほど総返済額を抑えることができます。金利タイプを決めたあとは、いくつかの金融機関を比較し、同じ金利タイプで金利水準の低い住宅ローンを選びましょう。
一般的に、実店舗を持たないネット銀行は、メガバンクをはじめとした実店舗型の金融機関と比べると金利が低い傾向があります。
特に公務員の場合は、住宅ローン審査における信用度が高く、最優遇金利(その金融機関が提示するもっとも低い金利)が適用されるケースもめずらしくありません。
3審査
![]()
公務員は住宅ローンの審査において、収入の安定性や信用面で有利です。ただし、転職して公務員になってから日が浅い場合(1年以内など)や、臨時職員・非常勤といった非正規職員の場合は、公務員であっても思い通りの審査結果が得られないケースもあります。
また、持病があって団体信用生命保険(団信)に加入できない場合も住宅ローン審査に影響することが少なくありません。
このように、審査面で不安がある場合は、審査の条件に勤続年数や雇用形態が含まれていない全期間固定型の住宅ローン「フラット35」が有力な選択肢に。フラット35には団信未加入で契約できるプランもあるため、団信が理由で住宅ローン審査に通りにくい場合も検討する価値があります。
4諸費用
![]()
住宅ローンの契約時には、金融機関に支払う「事務手数料」、土地・建物の「登記費用」、不動産購入に伴う「不動産取得税」、契約書に貼付する「収入印紙代」、保証会社に支払う「住宅ローン保証料」、「火災保険料」など、各種諸費用が発生します。
- 不動産取得税・印紙税
- 「不動産取得税」や「印紙税」のように、どの住宅ローンでも同額が発生する費用がある一方で、「事務手数料」「住宅ローン保証料」は金融機関による差が大きく、住宅ローンを比較する際は特に着目したいポイントです。
- 事務手数料
- 事務手数料は、借入額に一定割合をかける「定率型」と、1契約ごとの料金が決まっている「定額型」に分かれます。定率型の住宅ローンは、借入額が大きいほど手数料の金額も高くなるので、定額型の住宅ローンと迷った場合は、それぞれの銀行が用意しているシミュレーションで総返済額を比較してみましょう。

住宅ローンシミュレーションで複数の銀行を比較。イオン銀行、住信SBIネット銀行、ソニー銀行のシミュレーションを使って、実際の結果を元に各銀行の特徴を解説します。
- 住宅ローン保証料
- 住宅ローン保証料は、契約者が住宅ローンを支払えなくなった場合に、残債を肩代わりする保証会社に対して支払う手数料です。保証会社が間に入ることで、銀行は債務不履行のリスクを抑えられますが、その分、契約者が支払う諸費用はアップします。
最近では、保証会社を通さず、銀行自らが債務不履行リスクを負うことで諸費用を抑える住宅ローンが増えており、その場合は住宅ローン保証料が不要となります。
保証料不要の住宅ローンは、保証会社を使用する住宅ローンと比較すると審査が厳しくなる傾向がありますが、公務員は審査面で有利となるケースが多いため、保証会社を通さない(住宅ローン保証料が不要の)住宅ローンも積極的に検討してみると良いでしょう。

ネット銀行の住宅ローンの金利と手数料を比較!編集部のプロのおすすめは?
ネット銀行の住宅ローンを比較するポイントは?金利の低さは大きな魅力ですが、手数料の部分ではチェックしておきたいポイントも。利便性の高いサービスを提供しているネット銀行をピックアップし、それぞれの住宅ローンの特徴を比較しました。
5付帯サービス
![]()
民間金融機関の住宅ローンは、契約者向けに多くの付帯サービスを用意しています。
一部のネット銀行では、がんなど特定の病気にかかった場合に返済額の一部または全部が免除される特約を無料で団信に追加できます。
ほかにも、系列スーパーでの買い物が割引になる特典など、金融機関ごとにサービス内容が異なるため、銀行のホームページ等で確認してみましょう。
似た内容の付帯サービスでも、金融機関によっては有料(適用金利に上乗せetc.)になる場合や、適用条件等が異なる場合があるので注意が必要です。

特典が充実しているおすすめの住宅ローンは?買い物時の割引や、特約付き団信の無料付帯など、特典が充実しており、お得度が高いおすすめの住宅ローンを厳選して比較。
公務員におすすめの住宅ローンを比較
住宅ローン専門金融機関「ARUHI」が提供する全期間固定型の住宅ローン。フラット35のシェアは15年連続No.1。※1
自己資金(頭金)なしでも申し込みが可能な「フラット35」のほか、自己資金を1.5割以上用意する場合に金利引き下げを受けられる「スーパーフラット」も取り扱う。
なお、フラット35は保証会社を利用しないため、住宅ローン保証料は無料となっている。一部繰り上げ返済も手数料無料(10万円単位)。また、団信保険料は原則的に表示金利に含まれるが、団信なしプランを選択する場合は表示金利から0.2%引き下げとなる。
独自商品の「スーパーフラット」は、自己資金を多く用意するほど割安な金利が適用されるので、固定金利型で低金利の住宅ローンを探している場合はチェックしておきたい金融機関の一つだろう。
- 2010年度-2024年度統計、取り扱い全金融機関のうち借り換えを含む【フラット35】実行件数(2025年3月末現在、SBIアルヒ調べ)
- スーパーフラットをお申し込みの場合は「ご融資額×2.2%(消費税込)」
- 最低事務手数料220,000円(消費税込)
基本情報
| 事務手数料 | 定率型……借入金額の2.2%
|
|---|---|
| 住宅ローン保証料 | 無料 |
| 団信保険料 | 無料(団信ありの金利に含まれる) |
| 付帯サービス |
|
数ある金融機関のなかでも、トップクラスの実績と、利用者からの高い満足度を誇る「住信SBIネット銀行」の住宅ローン。
事務手数料は、借入金額の2.2%(税込)と高めだが、金利の低さはネット銀行の中でもトップクラス。住宅ローン保証料・団信保険料・一部繰り上げ返済手数料も無料となっている。
また、すべての病気やケガを保障する「全疾病保障」が上乗せ金利なしで基本付帯するほか、住宅ローン契約者が融資実行時に50歳以下の場合は、がん・脳卒中・急性心筋梗塞で所定の状態になった場合、住宅ローン残高の50%を保障する「3大疾病保障(※3大疾病50プラン/全疾病保障含む)」も上乗せ金利なしで基本付帯する。団信が充実しているのは、嬉しいポイント。
さらに、住宅ローン契約者は、住信SBIネット銀行のサービス利用状況に応じて振込手数料やATM手数料が月最大20回まで無料となる「スマプロランク」のランクアップ対象となる。住宅ローンはもちろん、家計のメインバンクとしても使い勝手の良い銀行の一つ。
金利 ※2026年1月実行金利
| 変動 | 年0.698%(通期引下げプラン) |
|---|---|
| 当初10年固定 | 年1.239%(当初引下げプラン) |
| 当初20年固定 | 年2.809%(当初引下げプラン) |
| 当初30年固定 | 年2.919%(当初引下げプラン) |
- 【新規・当初引下げプラン】表示金利は、最下限金利となります。(物件価格の80%以下で住宅ローンをお借入れの場合)
- 審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.3%上乗せとなる場合があります。
- 借入期間を35年超~40年以内でお借入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.07%、40年超でお借入れいただく場合は住宅ローン金利に年0.15%が上乗せとなります。
基本情報
| 事務手数料 | 定率型……借入金額の2.2%(税込) |
|---|---|
| 住宅ローン保証料 | 無料 |
| 団信保険料 | 無料
|
| 付帯サービス |
|
ネット銀行大手「住信SBIネット銀行」が取り扱うフラット35。「買取型」と「保証型」の2種類のフラット35を用意しており、いずれもインターネットを活用して申し込みから契約までの手続きを完結できる。
買取型は、事務手数料が借入金額の1.1~0.99%(税込)と割安で、自己資金が1割に満たない場合でも住信SBIネット銀行が提供する「フラットパッケージローン」を併用し、有利な金利でフラット35を借りられる。
保証型は、事務手数料が借入金額の2.2%(税込)とやや高くなるものの、自己資金を1割以上準備することで「買取型」よりも低金利でフラット35を借り入れることができる。団信にも無料で全疾病保障が付帯するなど付帯サービスも充実しているため、全期間固定型の住宅ローンを希望している場合は、有力な選択肢となるだろう。
買取型か保証型かを迷った場合は、住信SBIネット銀行のホームページ上にあるシミュレーションで総返済額を比較可能。フラット35を低金利で借りたい場合は候補に加えておきたい。
金利 ※2026年1月実行金利
| 15-20年固定 | 年1.71% |
|---|---|
| 15-20年固定 | 年2.08% |
- 融資比率9割以下/買取型の場合
- いずれも団信ありの場合。団信に加入しない場合は表示金利-0.2%
基本情報
| 事務手数料 |
|
|---|---|
| 住宅ローン保証料 | 無料 |
| 団信保険料 | 無料(団信ありの金利に含まれる) |
| 付帯サービス |
|
auフィナンシャルグループ(KDDIグループ)が提供するインターネット銀行「auじぶん銀行」の住宅ローン。変動金利型と固定金利選択型の住宅ローンを取り扱う。
住宅ローンの申し込みから契約まで、すべてをインターネット経由で行えるため、来店不要で住宅ローン手続きが完了する。
事務手数料は定率型で、借入金額の2.2%(税込)だが、住宅ローン保証料・一部繰り上げ返済手数料は無料。
また、auじぶん銀行では、住宅ローンと「au回線」「じぶんでんき」をセットで契約すると、住宅ローン金利を最大年0.1%優遇する「au金利優遇割」を提供している。できるだけ有利な金利で住宅ローンを組みたい場合、上手く活用すると良いだろう。
金利 ※2026年1月実行金利
| 変動 | 年0.834%(全期間引下げプラン)
|
|---|---|
| 10年固定 | 年1.550%(当初期間引下げプラン) |
| 20年固定 | 年3.060%(当初期間引下げプラン) |
| 30年固定 | 年3.605%(当初期間引下げプラン) |
- 【変動・新規】50歳以下のお客さまが一般団信を選択し物件価格の80%以下でお借入れの場合、年0.344%となります
- 審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。
金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。
基本情報
| 事務手数料 |
|
|---|---|
| 住宅ローン保証料 | 無料
|
| 団信保険料 | 無料
|
| 付帯サービス |
|
公務員でも住宅ローン審査に落ちるケースとは?
雇用や収入が安定しており、住宅ローン審査において有利だと言われる公務員ですが、100%の確率で住宅ローン審査に通過できるわけではありません。公務員であっても、住宅ローン審査に落ちるケースはあります。
例えば、以下に該当する項目がある場合は、公務員でも住宅ローン審査に通過するのが難しいくなると考えて良いでしょう。
- 個人の信用情報に問題がある
- 住宅ローンを提供する金融機関は、借り入れを希望する顧客のクレジットカードの返済情報や、カードローンの利用状況等を信用調査機関に確認する。その際、ローン残高が多い場合や返済遅延の履歴がある場合は、住宅ローン審査の際、不利になる可能性が高くなる (※ちなみに金融機関によっては、クレジットカードに付帯する「キャッシング枠」も借り入れ金とみなす場合も。住宅ローンの借り入れを検討する際は、不要なクレジットカードは解約する、キャッシング枠は0円に変更しておくのがおすすめ)
- 健康状態に何らかの問題がある
- 住宅ローンの借り入れには団信(団体信用生命保険)への加入が必須となっており、健康状態に何らかの問題があると、団信に加入することができないため
- 借り入れ希望額が多い
- 住宅ローン審査では、年収と返済額のバランスが重視され、一般的に年収の25~35%程度が年間返済額の目安となっている→借り入れ希望額がこのバランスを上回らないようにすることが大切
公務員で住宅ローン審査に落ちてしまう場合は、上記の内容をクリアできているかを確認したうえで、住宅ローン審査に申し込むのがおすすめです。